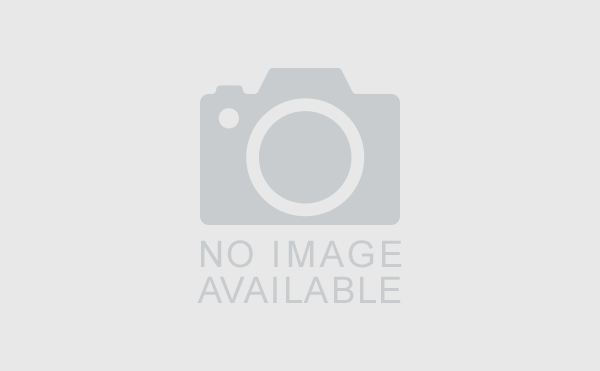SNSでも必要!動物取扱業の広告ルール
最近、ペットの販売・譲渡などSNSを活用されることが増えています。
Instagramでの写真投稿やX(旧Twitter)での販売告知、YouTubeでの紹介動画など、飼い主様との出会いの場がオンラインに移行しているのは自然な流れでしょう。
しかし、動物取扱業者が広告を行う場合には、紙媒体であろうとWebサイトであろうと、動物愛護管理法に基づく遵守事項を守らなければなりません。SNSも広告に該当するケースがあるので、注意が必要です。
ちなみに、トリミングサロンなどをフォローするとかわいいワンちゃんが自分のSNSに大量に流れてくるので心の癒しにつながるというちょっとしたライフハック。(余談)
※本稿における動物取扱業は主に「第一種動物取扱業」を指します。
動物取扱業の広告の遵守事項は?
”「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」第二条(第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準)七のケ”にて下記のように定められています。(以下、「規定」とします。)
ケ 第一種動物取扱業の実施に係る広告については、次に掲げる方法により行うこと。
(1) 氏名又は名称、事業所の名称及び所在地、第一種動物取扱業の種別、登録番号並びに登録年月日及び登録の有効期間の末日並びに動物取扱責任者の氏名を掲載すること。
(2) 安易な飼養又は保管の助長を防止するため、事実に反した飼養又は保管の容易さ、幼齢時の愛らしさ、生態及び習性に反した行動等を過度に強調すること等により、顧客等に動物に関して誤った理解を与えることのない内容とすること。
この規定についてはいわゆるチラシやリスティングなどの広告は当然ながら、ホームページ、ブログ、SNSも該当すると考えられます。
大阪動物管理センター分室が作成した「第一種動物取扱業を始める方へ」という冊子にも該当する旨の記載があります。
ホームページでは比較的掲載されているケースが多いですが、SNSだと皆さん掲載してないんじゃないでしょうか。
「SNSだから大丈夫」は通用しない
よくある誤解に「SNSは広告ではなく、単なる日常の投稿だから規制はかからない」というものがあります。
しかし、動物の販売や譲渡など営業活動を目的とした内容であれば、「広告」と見なされる可能性は高いでしょう。
特に次のようなケースはよく拝見しますが、注意が必要です。
- 販売中の子犬・子猫の写真を掲載し、問い合わせを受け付ける
- トリミングサロンのカット後の写真の投稿と店舗の紹介
- 猫カフェなどの混雑状況のアナウンス
すべてケースバイケースというか行政の判断にはなるのですが、注意されてから対応するというよりも、営業活動の一環でSNSをされているということであれば基本広告だと捉えておく方がよいのではないかと個人的には考えております。
よって、規定(1)の必要事項の表示を行うのがお勧めです。
誇大な広告の禁止
前述の規定(2)のように事実に反したものはもちろん、愛らしさなどを過度に強調することも認められません。
動物取扱業に従事される専門家はもちろん、ペットと現在暮らしている人なら趣旨はおわかりだろうと思います。
動物は可愛さだけではありません。
残念ながら、安易な気持ちで動物をお迎えされ、終生飼養がなされないケースも散見されます。
不幸な動物を少しでも減らす為、飼い主様に動物のこと、その子の個性を理解いただくことは非常に重要です。
景品表示法の兼ね合い
前述の規定の趣旨とはちょっと違いますが、誇大広告などは景品表示法上問題になるケースもあります。
平成の終わりに某大企業がトリミング・ペットホテルの宣伝で措置命令を出されたこともあります。
尚、本件については事実と異なることを広告していたことが問題になりました。
1.トリミングで全て炭酸泉シャワーを使っています。
→使ってないケースがありました。
2.ホテルではお散歩朝夕2回です。
→できていない場合があった。
消費者側の注意点
消費者の方々も広告については注意すべきと考えます。
というのも、広告に必要事項を掲載していない方々が、本当に動物取扱業者であるのかを確認する必要があるからです。
動物取扱業は広告だけでなく、様々な遵守事項を課せられています。
それは、動物たちの福祉に配慮し、誤った飼養管理が行われないようにするためです。
仮に無登録の業者であれば、その遵守事項を理解している保証はありません。
大事な家族を迎え入れたり、預けたりする相手ですから、消費者も注意深く相手を選ぶ必要があります。
尚、動物取扱業者の一覧は各自治体のホームページなどで公開されています。
実務のお話
事業者の方は、SNSやWebを活用する際には次の工夫をおすすめします。
- プロフィール欄に必須事項をまとめて記載する
- 広告テンプレートを用意して記載漏れを防ぐ
広告規制で突然重い処分が科せられるケースは稀でしょうが、今はコンプライアンスに厳しい時代ですし、ネガティブなお話は好ましいものではありません。
レピュテーションリスクの問題として、適切な広告かどうか、随時確認すべきですし、仕組化してミスを防ぐことがお勧めです。
まとめ
動物取扱業の規制は、消費者を保護し、動物の適正な取扱いを確保するための重要なルールです。
SNSの普及により、広告の場はますます多様化していますが、オンラインであってもオフラインと同じ義務が課されることを忘れてはいけません。
事業者は正しい表示を徹底し、消費者もまた動物についてはもちろん、事業者の選定について知識を得ることで健全なペット業界の発展につながっていきます。
尚、動物病院の場合獣医療法の規制もありますので、動物取扱業の兼業の際はよりお気を付けください。