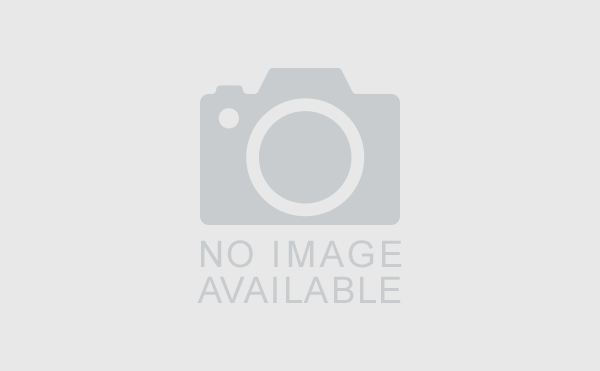会社を設立したい!「定款」って何?
「会社の定款」とは何か
会社設立を検討されている方にとって、「定款」という言葉は避けて通れない重要な用語です。
しかし、いざ「定款とは何ですか?」と聞かれると、漠然と「会社のルール」と理解していても、具体的にどのような役割を持ち、どのように作成しなければならないのかを正確に説明できる方は少なくありません。
今回は行政書士事務所の視点から、会社の定款について詳しく解説してみたいと思います。
※本コラムは、発起設立の株式会社(すごく一般的な会社設立と思っていただければ)を前提として記載しています。
定款とは「会社の憲法」]
定款は、会社を設立する際に必ず作成しなければならない基本規則です。
よく「会社の憲法」とも言われ、会社の組織や運営に関する根本的なルールを定める役割を果たします。
定款に記載すべき事項には、大きく分けて以下の3種類があります。
絶対的記載事項
会社法によって必ず記載しなければならない事項です。
これが欠けていると定款そのものが無効になります。
具体的には次のような内容です。
- 目的(会社が営む事業の内容)
- 商号(会社名)
- 本店所在地
- 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
- 発起人の氏名または名称
相対的記載事項
法律上、記載がなくても定款としては有効ですが、記載しておくことで効力を生じるものです。
例えば、株式譲渡制限、役員の任期、公告の方法などが該当します。
会社法で一応のルールが定まっていて、定款で別の定めができる項目だと理解してください。
めっちゃいっぱいありますのでここで列記することは避けます。
任意的記載事項
上記以外のものが任意的記載事項になります。
会社法などの規定に違反しない程度で、会社のルールとなります。
株主名簿の基準日や、取締役の員数などが該当します
定款作成と認証の流れ
株式会社を設立する場合、作成した定款は公証役場で「認証」を受ける必要があります。
この認証は原則発起人全員で行くもので、事前予約が必要です。
尚、電子認証という方法もあります。
詳しくは公証役場に聞いてみると親切に教えてくださいます。
もしくは個別にご質問ください。
定款の重要性と実務的ポイント
定款は一度作成したら終わりではありません。
会社の事業拡大や組織変更の際には、内容を変更することもあります。
例えば、事業目的を追加する場合や、本店を他の市区町村に移転する場合などは、株主総会の特別決議を経て定款変更を行います。
実務上、定款の目的をどう書くかは非常に重要です。
許認可が必要な事業を行う場合、基本的に目的に記載しておく必要があります。
また、行う予定がある事業は書いていた方がよいでしょうが、たくさん書きすぎると銀行や取引先から「何をしている会社なのか分かりにくい」と評価されることがあります。
行政書士としては、将来的な事業展開も見据えたうえで、適度に広がりのある目的を記載することがお勧めです。
行政書士事務所に依頼するメリット
会社設立に関する手続きはご自身でも可能ですが、法律用語や書式の厳密さを考えると、専門家に依頼するメリットは大きいです。
特に定款は会社の基盤を形づくる重要書類ですから、将来的に問題が生じないよう、行政書士がサポートすることで安心感が増します。
また、当たり前ですが定款は作って終わりではなく、銀行など外部に提出することもあります。
その際に作成した定款が「どう見えるか」を客観的に判断できるのも士業に依頼するメリットかもしれません。
また、
- 電子定款によるコスト削減
- 事業内容に合わせた目的条項の提案
- 公証役場とのやり取りの代行
- 設立後の定款変更や事業運営に関する継続的な相談
これらの点からも、特に許認可が必要な業務において、定款に関する業務は行政書士事務所に依頼するのがお勧めかと思います。
一方、特段許認可のいらないものであれば登記までまとめて司法書士さんに依頼する手もあります。
金額は一般的にはやや高めかもしれませんが、トータルでサポートしてもらえるのは大きなメリットです。
司法書士さんと行政書士で組んで会社設立業務を行う場合もあります。
まとめ
定款は会社の設立・運営に欠かせない「憲法」であり、会社の存在そのものを支える重要な文書です。
適切に作成し、必要に応じて柔軟に変更していくことが、健全な会社経営につながります。
行政書士はそのサポート役として、依頼者の事業を法的基盤から支える存在です。
これから会社を設立しようと考えている方、あるいは既存の定款を見直したいと感じている方は、ぜひ一度専門家にご相談ください。
当所では、フォームに入力いただければ定款の草案を行政書士が作成する窓口をご用意しております。
原則翌営業日~3営業日以内にご提出いたしますので、是非ご活用ください。
(通常は有料のサービスになります。現在テスト中の為、2025年10月末まで又は利用が5名様に達するまで無料にて実施しております。無料期間は早期終了の場合もあります。)