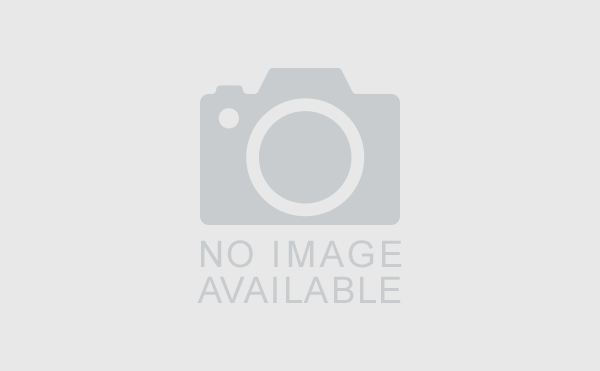業務委託を装った雇用契約とトリマー業界の現状
近年、ペット関連サービスの需要が拡大し、トリミングサロンの数も増加しています。
(知り合いのところは皆予約でいっぱいで、まだまだ足りない気もしますが。)
こうした中でよく耳にするのが「トリマーを業務委託で雇っている」という形態です。
一見すると自由度が高く、経営者・トリマー双方にメリットがありそうに思えますが、実際には「業務委託契約を装った雇用契約」として法的トラブルに発展しかねない例も増えています。
今回は、業務委託と雇用契約の違いを整理しつつ、トリマー業界における注意点を解説します。
注:本コラムではあくまでも一般論について記載しております。実際の個別の契約について、雇用契約か業務委託契約かの明確な判断は専門知識がなければ非常に難しいです。疑問を感じられている方は弁護士等に相談されることをお勧めします。
業務委託と雇用契約の違い
まず基本的な違いを確認しましょう。
雇用契約
労働者が使用者(雇い主)に対し、労務の提供を約束し、これに対して使用者が労働者に報酬を支払う契約です。(民法六百二十三条)
労働基準法や最低賃金法、社会保険制度などの適用対象となります。
尚、労働基準法上の労働者は「職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」となっています。
他の法令にもそれぞれ定義があり若干の違いはありますが、ざっくりと理解していただいて結構かと思います。
業務委託契約(請負・委任)
仕事の完成や一定の業務遂行を約束する契約で、労働基準法の適用はありません。
報酬は「成果」に応じて支払われ、労働時間の管理も基本的には行われません。
したがって、例えば「使用者の指揮命令下で働き、時間・場所を拘束される」場合は雇用契約と判断されることもあります。
契約書のタイトルが「業務委託契約書」となっていても、実態が雇用であれば雇用契約とみなされるのです。
トリマーにおける「業務委託契約」の実態
実際に見られるケースとしては、以下のような形が典型です。
- 出勤時間や休日がサロン側で指定される
- 使用するシャンプーやカット方法など、細かく指示がある
- お客様への対応方法まで細かくマニュアル化されている
- 報酬が「歩合制」とされているが、実態は時給や日給に近い
こういうケースでは、一見「委託」のように見えても、内容は「雇用」に近くなってきます。
つまり、「業務委託という名目を使って、経営者が何らかのメリットを得ようとしている。」という構造が浮かび上がってきます。
それがトリマーにとってもメリットのある話なら、仮に法令に違反したとしても揉めることはないでしょうが、労働者は非常に手厚い保護があるので、原則的にはトリマーにはメリットの薄い話になりがちです。
なぜトリマーで業務委託が増えているのか
理由はいくつか考えられます。
人材不足への対応等
トリマーは慢性的に人材不足の事業者も多いです。
業務委託契約とすることで、経営者は正社員より柔軟に人材を確保しやすくなります。
社会保険料などのコスト削減
雇用契約に比べ、社会保険・労働保険の負担を避けられると考える経営者がいます。
(私が以前勤めていた某企業もそうでした。さすがに止めましたが。)
自由度を求めるトリマー側のニーズ
トリマーの中には「複数のサロンで働きたい」「フリーランスとして活動したい」という方もおり、委託契約のほうが都合が良いケースもあります。
もっとも、個人的な印象では経営者側の「コスト回避」が大きな動機になっているケースが少なくないような気がしています。
偽装業務委託のリスク
業務委託契約を装っていても、実態が雇用であれば「労働契約」として扱われます。
その場合、次のようなリスクが生じます。
未払残業代請求
委託とされていたとしても、労働基準法上の労働時間管理義務が生じ、残業代の請求を受けることがあります。
社会保険・労働保険の遡及加入
偽装業務委託と認定されれば、過去に遡って保険料を支払う可能性もでてきます。
それぞれの法律の罰則等
雇用契約には労働基準法や最低賃金法など様々な法律が絡んでおり、罰則の適用をうける恐れもあります。
トリマー・経営者双方に必要な意識
トリマー側
契約書の「名称」に惑わされず、自分がどのような働き方をしているのかを冷静に確認する必要があります。
出勤や業務内容が強く拘束されているなら、それは実態として「雇用」となる可能性もあります。
経営者側
法令の不知によるものでも見逃してもらえるわけではありません。
また、「わかっていてやっている」方もいらっしゃるでしょうが、後に大きなリスクを抱え込むことになりかねません。
本当に委託として成り立つのか、契約内容を精査することが求められます。
余談ですが、私にも何度か本件のような業務委託について、トリマー側から相談を頂戴しています。
行政書士業務ではないので弁護士さん等を案内しますが、今後こういうトラブルが増えていくのではないかと懸念しています。
まとめ
トリマーをはじめ、ペット業界で広がる「業務委託契約」は、うまく活用すれば双方にメリットがあります。
しかし、実態が雇用であるにもかかわらず「委託」として処理するのは、実態は雇用契約とみなされ、重大なトラブルの火種となります。
大切なのは「契約書の名称」ではなく「実態」です。
働く側・雇う側の双方が正しい知識を持ち、適切な契約を結ぶことが、健全な職場環境と業界の発展につながります。
行政書士としては、契約書の作成・チェックの段階で相談いただくのが望ましいです。
トリマーに限らず、ペット業界全体で「契約の透明性」を意識していくことが必要でしょう。